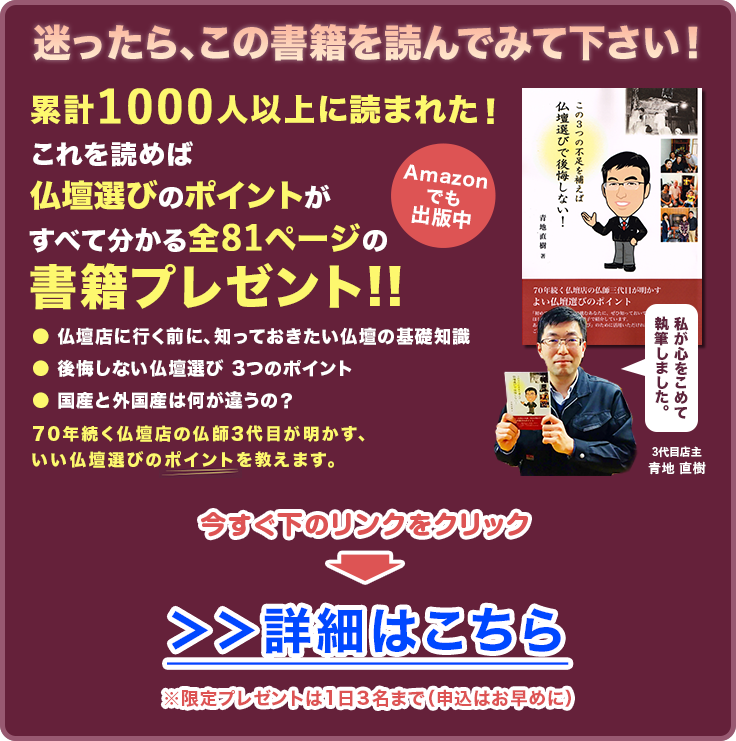日蓮宗の御宝前に幕を取り付けました。川崎の仏壇店
こんにちは
創業 昭和24年 仏師三代の
新川崎雲山堂
青地直樹です。
日蓮宗の御宝前に幕を取り付けました。
右側に日蓮宗の宗紋
左側に七面様の紋が入っております。
幕が付く事で、場が引き締まった雰囲気になり、
奥行感も増して、今まで以上にとても良い
御宝前になり、喜んで頂きました。
ありがとうございます。
是非動画をご覧ください。
お仏壇の、ご用命は新川崎雲山堂まで、
お気軽にご相談ください。
仏壇専門店 新川崎雲山堂
電話番号 044-555-2244
営業時間 9:30~18:30
定休日 水曜日
ホームページ https://s-unzando.com/