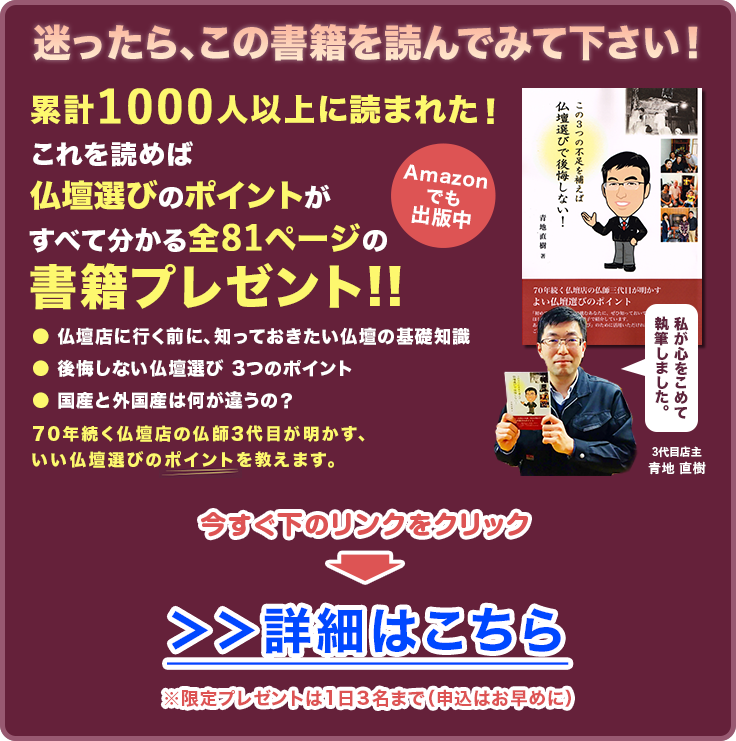【初めての位牌作り完全ガイド】四十九日までに何をする?費用・選び方・宗派の疑問をプロが全解決
ご安心ください。この記事を最後までお読みいただければ、初めてお位牌を作る方が抱えるあらゆる疑問が解消され、四十九日法要までに何をすべきか、その具体的なステップから費用の相場、宗派による違いまで、すべてを明確に理解できます。
この記事は、創業から70年以上にわたり、川崎市・横浜市・東京都大田区の地で1万基以上のお位牌作りをお手伝いしてきた仏壇・仏具の専門店「新川崎雲山堂」が、これまでの経験と専門知識を基に、責任を持って監修しています。
故人を偲ぶ大切なお位牌作りで後悔しないために、まずはこちらで全体像を掴んでいきましょう。
この記事で解決できること(結論の要約)
- Q. 位牌作りは何から始めればいい?
- A. まずは「①宗派と戒名の確認」「②位牌の種類とデザインの決定」「③納期と予算の決定」「④専門店への相談・注文」という4つのステップで進めるのが基本です。この記事で詳しく解説します。
- Q. 費用はいくらくらいかかる?
- A. 一般的な価格相場は3万円~20万円程度です。価格は素材や技法によって異なり、ご予算に合わせた選び方のポイントもご紹介します。
- Q. 宗派によって決まりごとはある?
- A. 多くの宗派で形に厳格な決まりはありませんが、一部注意点があります。特に浄土真宗の場合など、宗派ごとの特徴についても分かりやすく解説します。
- Q. 四十九日に間に合わない場合はどうすれば?
- A. 焦る必要はありません。間に合わない場合の具体的な対処法を3つご紹介しますので、ご安心ください。
それでは、一つひとつ丁寧に見ていきましょう。
まずはコレだけ!後悔しない位牌作り4つの基本ステップ
お位牌作りは、決して難しいものではありません。やるべきことを順番に整理すれば、誰でもスムーズに進めることができます。以下の4つのステップに沿って準備を進めていきましょう。
【ステップ1】宗派と戒名(法名)を確認する
お位牌作りで最も重要となるのが、表面と裏面に彫刻する文字の情報です。これらがなければ、お位牌を作ることはできません。
● 準備するもの
- 白木位牌(しらきいはい):ご葬儀の際に祭壇に置かれた、仮のお位牌です。ここには戒名(法名)、没年月日、俗名(生前のお名前)、享年(行年)など、必要な情報がすべて記載されてることがほとんどです。
※もし、上記の情報の中で白木位牌に記載されてないものがありましたら、予め分かるようにしてください。
※お家にご先祖のお位牌がある場合は、そちらの書式に従う場合がほとんどですので、その場合はご先祖の位牌も風呂敷などで包んでご持参ください。 - お付き合いのあるお寺(菩提寺)の情報:ご自身の家の宗派が分からない場合や、文字入れに関して確認が必要な場合に備え、連絡先を控えておくと安心です。
Q. 戒名(かいみょう)とは何ですか?
A. 戒名とは、仏様の弟子になった証として授けられる名前のことです。浄土真宗では「法名(ほうみょう)」、日蓮宗では「法号(ほうごう)」と呼ばれることもあります。故人が仏様のいる世界(浄土)へ迷わず辿り着くための、大切な道しるべとなります。
通常、白木位牌に書かれている情報から必要なものを本位牌に書き写しますが、お寺によっては独自のルール(梵字の有無など)がある場合もあります。可能であれば、一度、菩提寺の僧侶に「どのような内容で本位牌を作ればよいか」を確認しておくと、最も確実で安心です。
Q. 菩提寺がない場合はどうすればいいですか?
A. 特定のお付き合いのあるお寺がない場合でも、お位牌を作ることは全く問題ありません。その際は、ご葬儀でお世話になった僧侶に確認するか、私たちのような仏事の専門家にご相談ください。近年では、戒名を授からず、生前のお名前(俗名)でお位牌を作る「俗名位牌」を選ばれる方も増えています。
【ステップ2】位牌の種類とデザインを決める
お位牌には、伝統的な形から故人らしさを表現できる華やかなものまで、様々な種類があります。お仏壇の有無や、お部屋の雰囲気に合わせて選びましょう。
位牌の主な種類
お位牌は、大きく分けると「塗り位牌」「唐木位牌」「蒔絵位牌」の3つに分類されます。
| 種類 | 特徴 | こんな方におすすめ |
|---|---|---|
| 塗り位牌 | 檜や朴などの木地に漆を塗り重ね、金箔や金粉で装飾を施した、最も伝統的で格式の高いお位牌。深い黒の艶と金の輝きが特徴。 | ・格式を重んじたい方・伝統的なお仏壇をお持ちの方・親族からの理解を得やすいものを選びたい方 |
| 唐木位牌 | 黒檀(こくたん)や紫檀(したん)といった、硬く木目が美しい高級木材をそのまま活かして作られたお位牌。重厚感と耐久性に優れる。 | ・木の温もりを感じたい方・重厚で落ち着いた雰囲気がお好きな方・家具調仏壇にも合わせやすい |
| 蒔絵位牌 | 塗り位牌の表面に、漆で絵柄を描き、金粉や銀粉を蒔いて仕上げる伝統技法を用いたお位牌。故人が好きだった花などを描ける。 | ・故人らしい、パーソナルなものを選びたい方・手を合わせるたびに心が和むような位牌が欲しい方・華やかさや優しさを表現したい方 |
新川崎雲山堂が“本物”の塗り位牌・蒔絵位牌をおすすめする理由
私たち新川崎雲山堂では、数あるお位牌の中でも、特に日本の職人が作る「会津塗り」の漆塗り位牌や蒔絵位牌をおすすめしています。 なぜなら、お位牌は故人の魂が宿る大切なものであり、お家で毎日手を合わせ、共に過ごす存在だからです。
一見すると同じように見える黒いお位牌でも、実は「素材」「技法」「仕上げ」に大きな違いがあります。
- 素材(木材):安価な海外製の多くは、その時々で手に入る様々な木材を使うため材料を特定できません。 当店の会津塗り位牌は、位牌に適した上質な朴木(ほおのき)や姫子松(ひめこまつ)を厳選して使用しています。
- 技法(漆塗り):安価なものは合成樹脂塗料(カシューなど)で仕上げていますが、当店の会津塗り位牌は、扱いが難しく時間もかかる“本漆”を使用しております。 これにより、深く優雅な艶と優れた耐久性が生まれます。
- 仕上げ(金箔・金粉):金色風の塗料ではなく、純度98%以上の本物の「金箔」「金粉」で加飾しています。 本物の金は、時が経っても色褪せることなく、気品ある輝きを保ち続けます。
専門店を訪れた際は、ぜひ店員にこう尋ねてみてください。
『このお位牌の材料はなんですか?』
この質問に、戸惑うことなく木材の名前を答えてくれるお店こそが、日本の職人が作る本物のお位牌を扱う、信頼できるお店の証です。
【ステップ3】納期と予算を決める
デザインと同時に、納期と予算についても考えていきましょう。
納期について
お位牌は、注文してすぐに持ち帰れるものではありません。戒名などの文字を彫る、あるいは書く作業が必要になるためです。
- 一般的な納期:約2週間~3週間
- 内訳:文字レイアウトの作成・確認 → 文字彫り・文字書き → 最終検品・お渡し
四十九日法要の日から逆算して、遅くとも法要の3週間前までには注文を済ませておくと安心です。もし、時間が迫っている場合でも、専門店によっては短納期に対応できるお位牌もありますので、諦めずに相談してみましょう。
予算について
お位牌の価格は、前述した「素材」「技法」「仕上げ」のほか、「サイズ」「加飾(蒔絵など)」によって変動します。
- 一般的な価格相場:30,000円 ~ 200,000円
ご予算を決めておくことで、数ある選択肢の中からスムーズに候補を絞ることができます。次の章で価格と選び方について詳しく解説しますので、そちらもご参照ください。
【ステップ4】専門店に相談・注文する
必要な情報がそろい、お位牌のイメージが固まったら、いよいよ専門店に相談・注文します。
● 注文時に伝える・持参するものリスト
- 戒名(法名)、没年月日、俗名(生前のお名前)、享年(行年)などの情報が分かるもの:白木位牌やその写真
- 先祖の位牌(※ある場合のみご持参ください。)
- 宗派
- 希望する位牌のデザイン・サイズ
- 予算
- 希望納期(いつまでに必要か)
インターネット通販でもお位牌を購入できますが、私たちは実店舗を持つ仏壇・仏具の専門店で購入することを強くおすすめします。
● 専門店で購入するメリット
- 実物を見て触れられる:素材の質感や金の輝き、大きさなどを直接確かめることができ、イメージとの相違がありません。
- 専門知識を持つスタッフに相談できる:宗派による細かな違いや文字入れのルールなど、プロに相談しながら安心して選ぶことができます。
- お仏壇とのバランスを確認できる:既にお仏壇がある場合、そのサイズやデザインに合ったお位牌を的確に提案してもらえます。
私たち新川崎雲山堂では、お位牌に関するあらゆるご相談を承っております。初めての方でもご安心いただけるよう、経験豊富なスタッフが一つひとつ丁寧にご説明し、故人にふさわしいお位牌選びを心を込めてお手伝いさせていただきます。
【相場を解説】位牌の価格は何で決まる?予算別の選び方
「お位牌の値段は、何によって変わるの?」というのも、多くの方が抱く疑問の一つです。価格の違いは、主に以下の5つの要素によって決まります。
● お位牌の価格を決定する5つの要素
- 素材(木材):黒檀や紫檀などの高級唐木材や、国産の良質な朴木など、木材によって高価になる傾向があります。
- 技法(塗り):合成塗料に比べ、塗り師の経験と技量が問われる本漆塗りは高価になります。また、数多くの、「炭研ぎ」「摺り漆」「磨き」を繰り返す漆工芸最高技法の「呂色仕上げ」はさらに高価になります。
- 仕上げ(加飾):職人が手作業で絵柄を描く「蒔絵(まきえ)」や、蓮華や面などに本金箔や本金粉の装飾が施されると価格は上がります。
- 工程:海外で製造工程の大部分を行い、日本で最終仕上げだけを行うものより、木地作りから加飾まで一貫して国内(特に会津など)で作られるものの方が高価になります。
- サイズ:一般的に、お位牌は大きくなるほど価格が上がります。
Q. 位牌の値段は平均でいくらくらいですか?
A. 位牌の価格相場は3万円から20万円程度が一般的です。 価格は主に、素材(黒檀や紫檀などの唐木、朴木など)、塗り(本漆など)、加飾(蒔絵や本金など)の有無によって変動します。シンプルなものであれば3万円前後から、漆工芸最高技法「呂色仕上げ」や、凝った装飾が施されたものになると20万円以上になることもあります。
予算別に見るお位牌の選び方
ご予算に合わせて、どのようなお位牌が選べるのか、具体的な目安をご紹介します。
【予算:3万円~5万円】シンプルで質の良い定番の位牌
この価格帯では、主にシンプルなデザインの唐木位牌や、塗り位牌の中でも並塗り仕上げの位牌、また、蒔絵位牌の中ではウレタン仕上げのものなどがあります。
- 塗り位牌:伝統的な「春日型(かすががた)」や「勝美型(かつみがた)」など、装飾を抑えたすっきりとしたデザインで並塗り仕上げのものが中心となります。
- 唐木位牌:黒檀や紫檀の美しい木目を活かした、シンプルで落ち着いた雰囲気のものが選べます。
- 蒔絵位牌:ウレタン仕上げのモダンなデザインのものが選べます。
- ポイント:シンプルながらも、故人を偲ぶ気持ちを込めるには十分な品質のものが選べる価格帯です。お仏壇のデザインに合わせて選びましょう。
【予算:5万円~10万円】国産の上質な素材や装飾が施された高品質な位牌
この価格帯になると、選択肢の幅が大きく広がります。国産、特に会津塗りの高品質なお位牌が中心となり、ふっくらとした塗り肌と艶、細部の作りに違いが現れてきます。
- 塗り位牌:台座に蓮華の彫刻が施された「角切葵(すみきりあおい)」「猫丸(ねこまる)」「千倉座(ちくらざ)」など、格式高いものが選べ、上塗り仕上げのものが中心となります。
- 唐木位牌:艶のある透漆を用いて仕上げる春慶塗り位牌や、台座の彫刻にが素晴らしい「角切葵(すみきりあおい)」「上等猫丸(じょうとうねこまる)」などが選べます。
- 蒔絵位牌:漆でしか出せない深みと光沢のある透漆塗り仕上げや黒漆塗りのお位牌に、ワンポイントで季節の花などをあしらった、優しく上品なデザインのものが選べるようになります。
- ポイント:品質と価格のバランスが最も良いとされる価格帯です。長く受け継いでいくものとして、多くの方がこの価格帯のお位牌を選ばれます。
【予算:10万円以上】職人技が光る最高級の位牌
熟練した職人の手仕事によって作られる、美術工芸品ともいえるお位牌です。
- 塗り位牌:漆工芸の中で最も工程数が多い仕上げ技法「呂色仕上げ」の位牌が選べます。数多くの「炭研ぎ」「摺り漆」「磨き」の繰り返しにより得られる、フシや刷毛跡の無い平面に表現される、すっきりと深みのある漆黒が最大の特徴です。
- ポイント:ご予算に余裕があり、故人のために最高のものを用意したい、あるいは、家の象徴として長く大切にしていきたいという方に選ばれています。
【予算:15万円以上】目に見えない下地まで職人の技とこだわりが詰まった極上の位牌
熟練した職人が目に見えない下地にまでこだわりぬいて作られる、「本呂色仕上げ」のお位牌です。
- 塗り位牌:本呂色の「本」は、本堅地下地の「本」です。本堅地下地とは、漆工芸では最も丁寧で堅牢な下地技法です。「布着せ」と呼ばれる麻布や寒冷紗を漆で貼り付ける技法を施し、木地の割れや歪みを防いだり、木目が漆膜表面に現れるのを防ぎます。
- ポイント:ご予算に余裕があり、漆工芸の中でも最高技法の位牌を用意したいという方に選ばれています。
【専門家からのアドバイス】
価格が高いものが一概に良いというわけではありません。最も大切なのは、故人を想い、ご遺族が納得して選ぶことです。ご予算の中で、故人のイメージに合う、あるいは「これなら毎日気持ちよく手を合わせられる」と思えるお位牌を見つけることが、何よりも重要です。
もし、選択に迷われた際は、私たち新川崎雲山堂にお気軽にご相談ください。それぞれの位牌が持つ価値やストーリーを丁寧にご説明し、お客様にとって最良の選択ができるようサポートいたします。
意外と知らない!宗派による位牌の違いと注意点
「うちの宗派だと、特別なお位牌が必要なの?」というご質問もよくいただきます。ここでは、宗派によるお位牌の違いや、特に注意が必要なケースについて解説します。
基本的にはどの宗派でも形に厳格な決まりはない
結論から言うと、ほとんどの宗派において、お位牌の形やデザインに「こうでなければならない」という厳格な決まりはありません。 そのため、前述した塗り位牌、唐木位牌、蒔絵位牌の中から、故人のイメージやお仏壇の雰囲気に合わせて自由に選んでいただいて問題ありません。
ただし、いくつか宗派ごとの特徴や慣習がありますので、知っておくとより安心です。
戒名(法名)の上の「梵字」
お位牌の表面、戒名(法名)の一番上に、宗派のご本尊様を表す**梵字(ぼんじ)**を入れることがあります。
- 天台宗:阿弥陀如来を表す「キリーク」
- 真言宗:大日如来を表す「ア」
- 浄土宗:阿弥陀如来を表す「キリーク」
- 臨済宗・曹洞宗(禅宗):成仏したことを表す「空」の文字や、釈迦如来を表す「バク」を入れることがある
- 日蓮宗:法華経を表す「妙法」の二文字を入れることがある
これらの梵字を入れるか入れないかは、菩提寺の考え方によって異なります。また、先祖の位牌に合わせることも多いです。 白木位牌に書かれている場合、書かれていない場合、どちらの場合でも確認が必要です。もし迷った場合は、必ず菩提寺に確認しましょう。
【最重要】浄土真宗は原則として位牌を用いません
数ある宗派の中で、唯一注意が必要なのが浄土真宗です。
Q. なぜ浄土真宗では位牌を使わないのですか?
A. 浄土真宗の教えでは、亡くなった方は阿弥陀如来の力によって、すぐに極楽浄土へ往生し仏になると考えられています。そのため、魂がこの世に留まり、供養のために位牌に宿るという考え方をしません。
そのため、浄土真宗ではお位牌の代わりに、仏壇の内部に「法名軸(ほうみょうじく)」という掛け軸を掛けるか、「過去帳(かこちょう)」という帳面に法名などを記して供養するのが正式な形です。
近年の傾向と代替案
しかし、現実的には「手を合わせる対象が欲しい」「他の宗派の親族への配慮」といった理由から、浄土真宗の方でもお位牌を祀るケースが非常に増えています。
また浄土真宗の一部の寺院や一部の宗派では、お位牌を作る必要がある場合もあります。このように、浄土真宗であっても、お位牌を「作る」「作らない」「どちらでもよい」というのは、お寺のご住職により考え方がさまざまですので、一度所属するお寺にご相談していただくことをおすすめします。
Q. 自分の家の宗派が分からない場合はどうすればいいですか?
A. まずはご両親やご親族に尋ねてみましょう。それでも分からない場合は、ご葬儀でお世話になった僧侶に問い合わせるか、ご先祖様のお墓があるお寺(菩提寺)に確認するのが確実です。お仏壇がある場合は、ご本尊様(仏像や掛け軸)の形式からもある程度推測することが可能です。
間に合わない!と焦る前に。四十九日法要と位牌の納期Q&A
「うっかりしていて、四十九日法要まで時間がない!」
初めてのことで、準備が遅れてしまい焦っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。ここでは、納期に関する疑問と、万が一間に合わない場合の対処法をQ&A形式で詳しく解説します。
Q. なぜ「四十九日まで」に本位牌が必要なのですか?
A. 仏教では、故人の魂は亡くなってから四十九日間、この世とあの世の間を旅しているとされています。そして、四十九日目に閻魔大王の最後の審判を受け、来世の行き先が決まります。この四十九日法要は、故人が無事に極楽浄土へ行けるように祈る、非常に重要な儀式です。
法要では、それまで故人の魂の依り代(よりしろ)であった白木位牌から、これから永代にわたって祀っていく本位牌へと魂を移す「開眼供養(かいげんくよう)」または「魂入れ(たましいいれ)」という儀式を僧侶に行ってもらいます。この儀式があるため、四十九日法要までに本位牌を準備する必要があるのです。
Q. 注文から完成まで、平均でどのくらいの期間がかかりますか?
A. 一般的に2週間から3週間ほどかかります。 文字のレイアウトを作成し、お客様にご確認いただいた後、専門の職人が一文字ずつ丁寧に彫刻、または書き入れていきます。特に、手書きの場合は乾燥に時間が必要です。その後、間違いがないか厳しく検品してお渡しとなるため、ある程度の期間が必要となります。
Q. どうしても四十九日法要に間に合わない場合、どうすればいいですか?
A. 焦らないでください。万が一、本位牌の準備が法要に間に合わない場合でも、3つの対処法があります。
- 対処法1:まずは菩提寺や僧侶に正直に相談する
- 最も大切なことです。事情を説明すれば、ほとんどの僧侶は柔軟に対応してくださいます。「法要は一旦、白木位牌のまま行いましょう」といったご提案をいただけます。
- 対処法2:法要を仮の位牌(白木位牌)で行い、後日「魂入れ」を行う
- これが最も一般的な対処法です。四十九日法要そのものを取りやめる必要は全くありません。法要は予定通り行い、後日、本位牌が出来上がったタイミングでお寺に持参し、個別に魂入れの供養をしていただきます。
- 対処法3:納期が早い位牌を選ぶ(専門店に相談)
- 専門店によっては、職人との関係性が良好な場合、特別に比較的短納期で対応可能な場合があります。「〇月〇日の法要に間に合わせたい」と具体的な日付を伝えて相談すれば、最適な提案してくれる可能性があります。
Q. 間に合わせるために、注文時に気をつけることはありますか?
A. スムーズに注文を進め、納期遅れを防ぐために、以下の2点を心がけましょう。
- 戒名(法名)などの情報を正確に準備しておく
- 白木位牌及び先祖の位牌の持参(できなければ、それぞれの表裏両面の写真を持参)するなど、文字情報に間違いがないように準備します。文字の確認に時間がかかると、その分納期も遅れてしまいます。
- 「いつまでに必要か」を最初に明確に伝える
- お店のスタッフに「四十九日法要が〇月〇日なので、それまでに受け取りたい」と最初に伝えることが重要です。これにより、スタッフも納期を最優先に考えて対応してくれます。
川崎市・横浜市で位牌の相談なら創業70年の新川崎雲山堂へ
ここまで、初めてお位牌を作るための手順や知識を詳しく解説してきました。しかし、いざ自分で選ぶとなると、やはり不安や迷いは尽きないものです。
もし、川崎市や横浜市、またその近郊でお位牌選びにお困りでしたら、ぜひ一度、私たち「新川崎雲山堂」にご相談ください。 私たちが、多くのお客様から信頼を寄せられ、選ばれ続けているのには理由があります。
【理由1】“本物”へのこだわり。職人の手仕事が光る会津塗り位牌
私たちは、故人の魂が宿り、ご家族がこれから毎日手を合わせるお位牌だからこそ、それにふさわしい“本物の品質”であるべきだと考えています。 そのため、安価な海外製の位牌ではなく、熟練した日本の職人が作る、最高品質の「会津塗り位牌」を自信を持ってお勧めしています。
- 厳選された国産木材:位牌に適した上質な朴木や姫子松を使用。
- 伝統の漆塗り技法:深く優雅な艶と耐久性を併せ持つ、本漆を使用。
- 色褪せない本物の輝き:純度98%以上の本物の金箔・金粉で仕上げています。
その違いは、手に取っていただければ必ず実感いただけます。 私たちの店舗で、ぜひ熟練した会津職人の“手の温もり”と“安心感”を感じてください。
【理由2】専門知識豊富なスタッフによる、親身なサポート
「宗派のことがよく分からない」「仏壇に合うサイズが知りたい」
初めてのお位牌作りは、分からないことだらけで当然です。当店は、経済産業省認可の全日本宗教用具協同組合「優秀店」であり、「仏事コーディネーター」資格を持つ専門スタッフが在籍しております。お客様一人ひとりの状況やご不安に寄り添いながら、最適なご提案をさせていただきます。
無理におすすめするようなことは一切ございません。お客様が心から納得し、故人を偲ぶ時間に安らぎを感じられるようなお位牌を見つけること、それが私たちの使命です。
【理由3】創業70年、川崎・横浜で培った信頼と実績
当店は、昭和24年に東京都大田区の地で初代が創業し、昭和61年に二代目がこの川崎・横浜の地にのれん分けし、創業から70年以上地域の皆様と共に歩んでまいりました。これまでに1万基を超えるお位牌をお客様にお届けしてきた実績は、私たちの何よりの誇りです。
長くこの地で商いを続けてこられたのは、一つひとつのお位牌、一人ひとりのお客様と真摯に向き合ってきた結果だと信じております。ご購入後のアフターフォローはもちろん、お位牌以外の仏事に関するお困りごとにも、長年の経験を活かしてご相談に応じています。「何かあったら新川崎雲山堂に聞けば大丈夫!」そう思っていただける、地域にとっての“駆け込み寺”のような存在でありたいと願っています。
まとめ:故人を偲ぶ大切なお位牌選び
最後に、この記事の要点をもう一度振り返ります。
- 位牌作りの基本は4ステップ:①宗派・戒名確認 → ②デザイン決定 → ③納期・予算決定 → ④専門店へ注文
- 価格の相場は3万円~20万円:価格は素材・技法・加飾などで決まる。大切なのはご予算内で納得のいくものを選ぶこと。
- 宗派による大きな違いは少ない:ただし、浄土真宗の場合は原則として位牌を用いないため、必ず菩提寺への確認が必要。
- 納期は2~3週間が目安:四十九日法要から逆算して、早めに準備を始めるのが安心。
- 間に合わなくても対処法はある:焦らず、まずは菩提寺と専門店に相談することが大切。
- 購入は専門店が最も安心:実物を確認でき、専門的なアドバイスを受けながら選べるメリットが大きい。
お位牌選びは、単なる「モノ」選びではありません。それは、亡き大切な方と心を通わせ、在りし日の姿を思い出し、感謝を伝えるための、かけがえのない時間です。
慌ただしい日々の中ではありますが、どうぞ少しだけ足を止め、故人様のお人柄や思い出に心を馳せながら、お位牌を選んでみてください。
私たち新川崎雲山堂は、皆様のお位牌作りが、後悔のない、心温まる時間となりますよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。どんな些細なことでも構いません。ご不安な点、ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお声がけください。
この記事の監修者
株式会社 新川崎雲山堂 体表取締役 青地 直樹
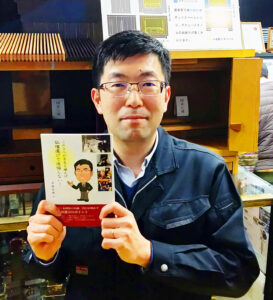
役職: 代表取締役 / 仏師三代目
経歴:
昭和24年創業の仏壇店「雲山堂」をルーツに持つ「新川崎雲山堂」の三代目。祖父、父の背中を見て育ち、幼い頃から仏壇・仏具に触れる。大学では建築学を専攻し、住宅デザインや動線計画を学ぶ。卒業後、家業を継ぎ、仏壇業一筋の道を歩む。経営者として悩んだ経験から「お客様の心に寄り添う」ことを経営理念の中心に据え、日々お客様と向き合っている。
保有資格:
- 二級建築士
- 仏事コーディネーター
お客様へのメッセージ:
「お仏壇は、特別なものではなく、日常生活の中に溶け込み、故人と共に暮らすための大切な場所です。私たちは、お客様が心から安らぎ、自然と手を合わせたくなるような、世界に一つだけの祈りの空間を創るお手伝いをさせていただきます。どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。